精製操作のハードルを最⼩化。超⾼速フラッシュ精製装置 Biotage® Selektで精製時間を⼤幅に短縮!
名古屋⼤学⼤学院理学研究科野依特別研究室
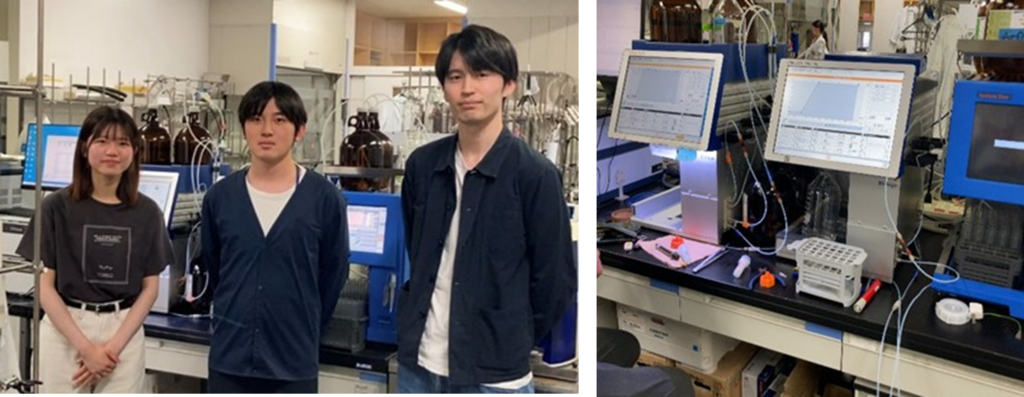
―精製の効率化を⽬指しBiotage® Selektを導⼊。チームとしての精製作業のイメージを⼤きく改善。―
名古屋⼤学⼤学院理学研究科野依特別研究室では「新触媒で未来をつくる」をテーマに、多彩な化学反応の実現を通じて、合成化学の基礎確⽴に貢献してこられました。現在では、野依良治特別教授(2001年ノーベル化学賞)の「時代が求める知は何か」という問いを念頭に、持続可能な社会の実現に向けた合成化学の開拓に挑戦しておられます。今回は超⾼速フラッシュ⾃動精製システム Biotage Selektシリーズを導⼊されておられる森彰吾助教にお話を伺いました。
―弊社の装置をご使⽤されている研究内容についてご説明いただけますか?
森先⽣:斎藤進教授が主導している研究室全体としては、有機合成化学に基盤を置きながら多様な研究が推進されています。キーワードとしては、⼈⼯光合成、光触媒、⾼分⼦のアップサイクリング、分⼦⾻格編集、機械学習、⽔素化、⼆酸化炭素の資源化などです。⼀つの研究室内とは思えないほどたくさんの異分野に触れる機会があり、刺激的な研究室だと⾃負しています。このような環境の中で私は、有⽤な有機化合物を合成するための⼈⼯光合成、すなわち「有機合成指向⼈⼯光合成」の研究を推進しています。また、学術変⾰領域研究AのSRePとい う枠組みの中では、すでに組み上がっている化学構造を後から任意に編集することで、多様で新奇な化学構造の迅速な構築を⽬指していま す。いずれの研究テーマにおいても新しい有機分⼦⾻格を⽣み出す中で、⾃動精製装置は⼤活躍です。
◆Selektを導⼊し新しい発⾒も!
―いろいろ環境に配慮したワードが並んでおり興味深いテーマですね。その中でBiotageの精製装置Selektシリーズを導⼊していただいた訳ですが、導⼊前はどのように精製を⾏っておられたのですか?
森先⽣:私がこの研究室に来た時には前世代の精製装置Isolera Oneが⼀台ありましたので、それとオープンカラムを併⽤していました。
―そういった中でSelektとSelekt Enkelを導⼊していただいた決め⼿は何でしょうか。
森先⽣:⼀番の決め⼿はSelekt、Enkelの送液速度が早いことです。カラム精製のスピードアップができました。反応開発をしていると、同じ化合物を分けることは少なく、毎回違う反応のクルードを精製します。常にリアルタイムUV検出クロマトを⾒つめ、欲しいものが来たら、そして違うものが混ざりそうになったら、フラクションを切り替える必要があります。Isolera OneのころはこのUV検出クロマトを⾒つめている時間が⻑かったけれども、最近はその時間がめっきり短くなったなあと感じます。
他にも導⼊の決め⼿はたくさんあります。例えば、Biotageさんの信頼感です。困ったら駆けつけてくれますし、初歩的な質問からなんでも付き合ってくれます。あと、装置が頑丈だということも重要です。これまで⼀度も装置不調を感じたことはありません。あとは若⼿研究者でもギリギリ⼿が届く予算規模なのもありがたかったです。
―決め⼿にBiotageへの信頼感といただきうれしい限りです。チームにも情報をシェアしたいと思います(笑)。実際どのような状況で使⽤していますか。
森先⽣:森グループの学⽣さんが半導体光触媒を使って新しい有機合成反応を開発する際にBiotageの精製システムを頻繁に使います。例えば⼈⼯光合成の要件を満たしつつ医薬品分⼦を合成する反応や、平⾯の芳⾹環⾻格を⽴体的な脂環式⾻格へと劇的に⾻格編集する反応です。
◆使いやすさに満⾜
―⼈⼯光合成という何とも魅⼒的なワードがまた出てきました。その中のどのようなステップで精製⼯程が重要な役割を持っていますでしょうか。
森先⽣:主に1 mmol以下のスケールの反応の⽣成物を単離する際に⽤いています。新しい反応の探索段階では、形成した化合物の構造決定が何よりも⼤切です。そのためにはクルードの中の主要な成分を部分的にでも短時間で単離する必要があります。(主要な成分の判断にはリアルタイムUV検出が役⽴っています)。Selektに限りませんが、Biotageの製品の魅⼒は分離能の⾼さとそれに起因する化合物をシリカに晒す時間の短さだと思います。シリカゲルに弱く分解してしまう化合物であっても、Biotageの製品を使えば完全に分解し切る前に分取し単離できることがあります。実際、ある研究テーマを⾒逃さなかったのは、Biotageの製品を使っていたからだと思います。少量ながら単離できた不安定な化合物がそのテーマのKeyとなる化合物だったのです。これに関してはとても感謝していますよ!もちろん、論⽂化の際にロスなく単離したいときにもBiotageの製品に は⼤活躍してもらっています。
―今回は研究室の⽅にもご同席していただいております。ぜひ⼀⾔お願いします。
加藤さん(M1):カラム操作のハードルが下がりました。オープンカラムに⽐べてとても楽なので、1⽇に何度でもカラムをやろうかという気になります。(笑)あと、準備や⽚付けの⼿間が短く、その時間をほかの作業に充てられます。PDAは化合物の構造をイメージしやすいので良く⾒ています。
伊藤さん(4年⽣):私はまだそんなに使⽤経験はないのですが、市販の純度が低い原料を使⽤前精製する時に使っています。繰り返し同じ化合物を精製する場合には、以前の実験条件を読み込んで、後は放置でいいので、楽だなと思っています。⼤きなカラムが⼿元にないので必要な分だけ精製している感じです。⼤きなカラムでやってみたいです。
―貴重な学⽣⽬線でのコメントありがとうございます。新しいソフトウェアではPDAを3Dで⾒ることができ、多くのフラクションを廃液ラインから任意のボトルで取ることのできるバイパストレイ機能などが実装されました。ぜひ試してほしいです!
―これから我々の装置でやってみたいことはありますでしょうか。
森先⽣:⼤きいスケールでの精製のノウハウがまだないので、取り組んでいきたいとおもいます。新しいソフトもよさそうですね。
―その他Biotage製品についてご要望などありますでしょうか。
森先⽣:⼤きいスケール⽤のカラムのお値段をもう少し可愛くしてほしいです。なかなか⼿が出ず、⼤スケールの時はオープンカラムをしています。あとカラムのラインナップや特徴の情報にアクセスしやすくなってほしいです。⼀覧表とかが⾒やすくなればいいですね。あと装置⾯では、我々のサンプルでは溶液が分取ノズルを上がってきて、ノズル上に化合物が析出することが多いです。拭き取ればいいことなのですが、ノズル形状の⼯夫でどうにかならないかな、と思っています。あるいは⾃動洗浄の機構とかがあったら嬉しいです。
―多くのご意⾒ありがとうございます。⼤きなスケールのカラムに関してはReningという廉価版カラムをご⽤意しております。⼀度お試しいただければと思います。ノズル洗浄については、貴重なご意⾒として今後の参考とさせていただきます。本⽇はお忙しい中、お時間をいただきましてありがとうございました。
インタビュー実施 2025/6/4
導⼊製品
超⾼速フラッシュ⾃動精製装置Biotage® Selekt
導⼊機関
名古屋⼤学⼤学院理学研究科野依特別研究室


東海国⽴⼤学機構の構成⼤学である名古屋⼤学は、1871年に設⽴された仮病院‧仮医学校を起源とし、1939年に最後の帝国⼤学として開学。
創⽴当初から受け継がれている「⾃由闊達」な学⾵を伝統とし、世界有数の産業集積地に根差して、社会連携‧産学連携により新たな価値を創造するとともに、⼈類課題‧社会課題解決に貢献することを⽬指して世界レベルの教育‧研究を実施している。


